集中治療科医とはー最重症患者さんの命をつなぎとめる“最後の砦”

ICU(集中治療室)には、心筋梗塞や肺炎、脳出血など原因も経過もさまざまな重症患者さんが集まります。
しかも「血圧が下がっている」「酸素化が悪い」「意識レベルが下がっている」「尿が出ない」など、
同時に複数の問題が発生することが当たり前。それらの問題は刻一刻と変化し、目が離せません。
集中治療科医は、そのような重症で生命の危機に直面した患者さんを全身管理の視点でサポートする医師です。
集中治療は診療科の枠を超えて、呼吸・循環・代謝・脳神経など多臓器にわたる重篤な病態に対応する必要があるため、
幅広い知識と冷静かつ的確な判断力が求められます。
多職種とのチーム医療が欠かせないのも、ICUならでは。
患者さんのためにみんなで力を合わせ、知恵を絞る場面が日々あり、その分やりがいは格別です。
高度な医学的アプローチによって、患者さんの命をつなぎとめる“最後の砦”でもあるのです。
救急科医との違いは?
集中治療科医と救急科医は、いずれも「緊急を要する患者さん」を相手にする場面が多いため、混同されがちです。
しかし主なステージが異なります。
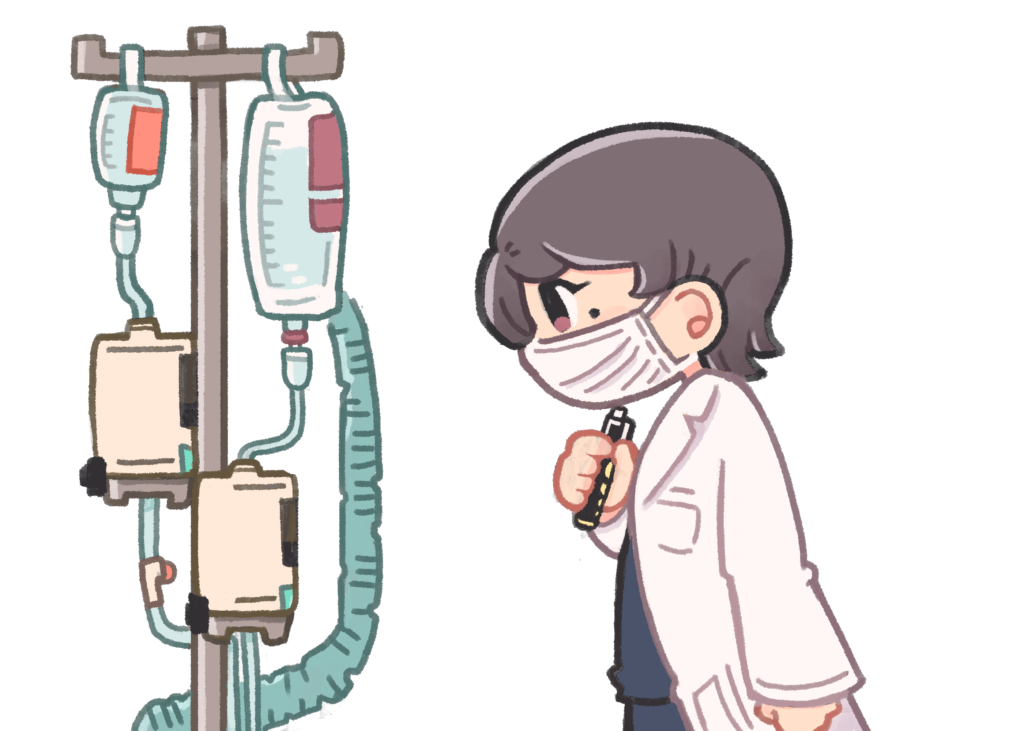

急患として搬送されてきた患者さんの初期治療を担当し、容体が安定するまでの緊急処置を迅速に行います。
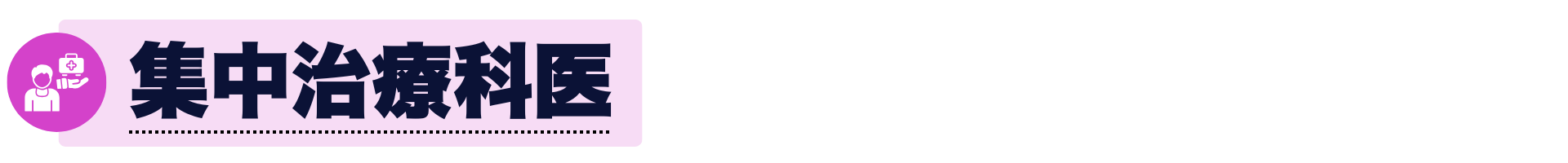
ICUに入室した患者さんの全身管理を主な仕事とし、状態が安定するまで24時間体制でサポートし続ける役割です。
もちろん、病院によっては救急科医が集中治療科医を兼任しているケースもあります。
なかには「ERでファーストタッチを担当し、ICUへ転科後も同じ医師が継続して管理する」流れを構築している施設も。
広島大学をはじめとする広島の救命センターでは、救急と集中治療を一連の流れで診療する施設が多いのが地域的な特色と言えます。
集中治療科医だからこそ味わえる“やりがい”


急変が絶えず起きる中で、全身管理の視点から最善の処置を考え、命を救うためにフル稼働する。
大変な現場ですが、そのぶん患者さんが快方に向かう瞬間の喜びは大きいです。

重症患者さんに対しては、内科的・外科的アプローチを横断的に活用しながら、緊急時の手技や全身管理を行わなければなりません。
広い視野をもちながら、ICU特有の専門技術(人工呼吸管理、循環管理、各種デバイスの操作など)を深めていくことができるのが集中治療の魅力です。

集中治療室に患者さんを預ける主治医にとっては、「安心して任せられる相手かどうか」が重大なポイント。
集中治療科医が的確な判断や処置を行い、患者さんの容体を好転させれば、担当医との間に強い信頼関係が生まれます。
病院内で「重症管理のプロ」として認識され、幅広い相談を受けるようになり、医師やスタッフ同士の連携も活発になるでしょう。

当院のICUのように近年はシフト制で働くICUも増え、オンとオフをしっかり切り替えながら働ける環境が整いつつあります。
夜間や休日のICU管理を集中治療医が担うことで、他の科の医師たちも休むべきときに休み、翌日の診療や手術に備えることができる。
結果的に院内全体の労働環境を改善する手助けにもなるのです。
どうやったら集中治療医になれる?
日本における集中治療科医のバックグラウンドとしては、麻酔科医と救急科医の2つが大きな割合を占めています(その他、小児科、内科からも専門医を習得することができます)。
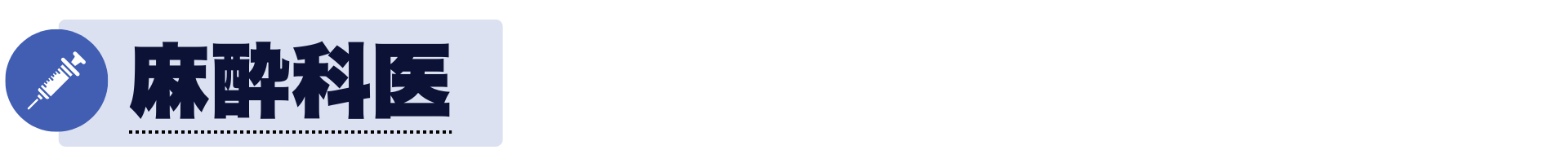
手術室での全身管理や術後管理を担当してきた経験が活かされ、重症の患者さんに対しても生理学的な知識を深く応用できる立場です。
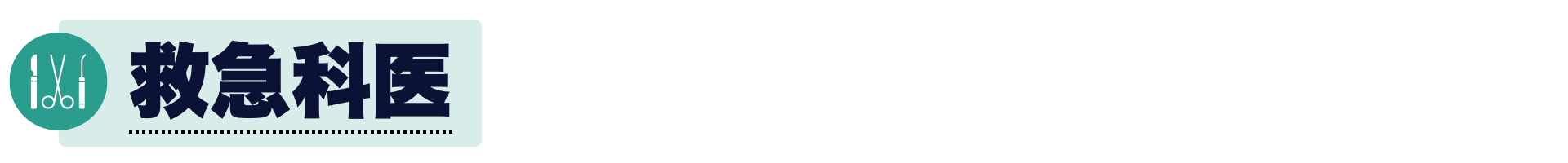
救急外来で重症患者さんを初期対応する実践経験が豊富なため、集中治療室での高度なケアにもスムーズに適応しやすい特徴があります。
ただし、これらに限らず内科や外科、脳神経外科などから集中治療の世界に進むケースも存在します。
重症管理に興味を持つ医師であれば、どの専門科の出身であっても道は開かれているといえます。
広島大学病院で集中治療科医を目指しませんか?
広島大学病院では魅力的な研修プログラムを準備しています。
